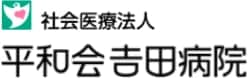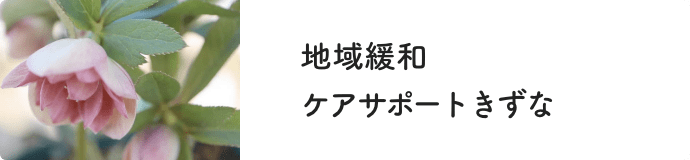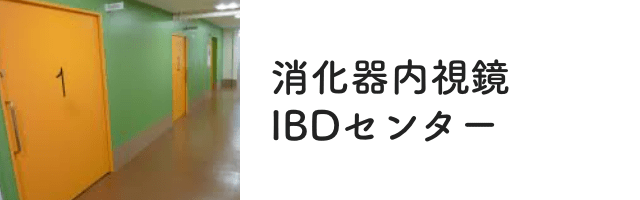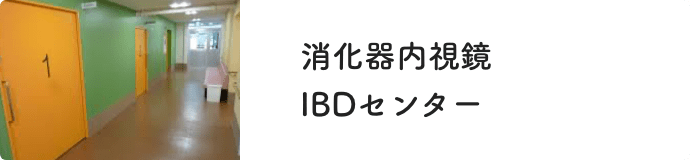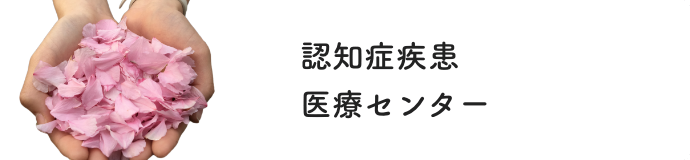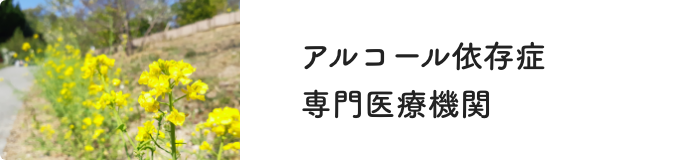お知らせ
news

- コラム
- 父と娘、たまに医師。 第3回
父と娘、たまに医師。 第3回

平和会地域緩和ケアサポートきずな
加納 麻子 (日本緩和医療学会 専門医)
緩和ケア医が、自身の父の最終章に関わってきた思いを綴るエッセー。6回にわたって掲載します。
「打つ手はもうないんだな」
新型コロナウイルス感染症が勢いを増し始めた頃、父は外出すらままならない程に疲れやすくなっていました。
感染のリスクを負ってまで主治医のいる病院へ受診することを、父はためらったので、代わりに私が主治医に会うことを提案しました。
治療に取り組んできたにも関わらず病状が悪化していることから、もはや改善する見込みがないことは明らかでした。とはいえ、父の主治医は専門的に前立腺癌の患者を数多く診ています。もしかしたら私では思いつかない何かがあるかもしれないと思い、助言を求めました。一時間ほど話し合いましたが、やはり期待できる術はみつかりませんでした。
夜、重たい心で実家に向かいました。
主治医に会ったことを伝えると、父はすっかり細くなった脚で正座をしました。私は検査結果を見せ、話し合ってきたことを伝えました。父は「打つ手はもうないんだな」と静かに言いました。私は涙で何も話せなくなりました。娘であり医師である私が幼い子のように嗚咽する。そのこと自体が腫瘍マーカーの値なんかよりも、父の病状を率直に伝えることになっていたのだろうと思います。
母が「そんな顔をお父さんに見せなさんな」と悲しそうに叱りました。その一方で父はいつもどおりでした。
心の内は見えませんが、きっと父はわかっていたのだろうと思います。自分の体の尋常ではない変化を、身をもって感じていたのは父自身なのですから。
打つ手がなくなっていることを父に伝えないという選択肢もあったのでしょう。でもその選択肢を、不思議と私は思いつきもしませんでした。何故か。それは父がそんなことを望む人ではないと自ずと感じていたからかもしれません。私が話さないままでいることを、私自身が許しませんでした。それまで父にとって娘なのか医師なのか、どう在るべきかをずっと悩んできました。しかし、娘であり医師である私を切り分けることなど出来ないと、やっと気付いた夜でした。

初夏に咲く無数の大手毬を父は愛でていました
サイト内ページ一覧