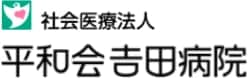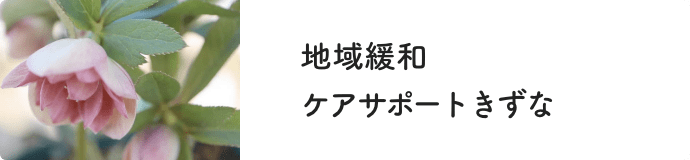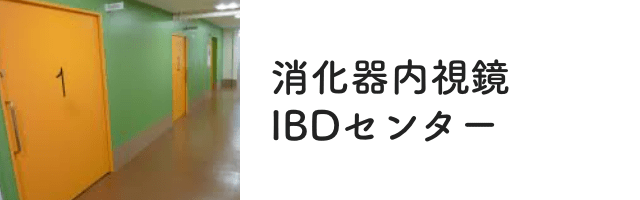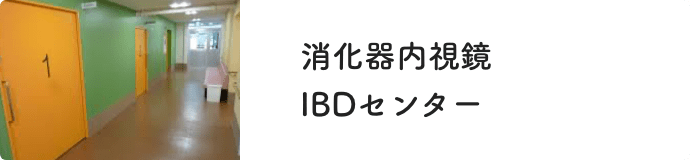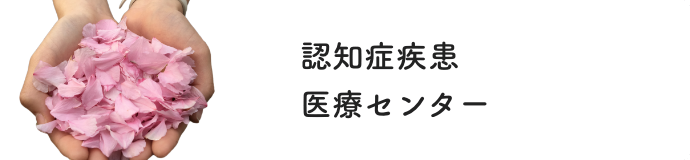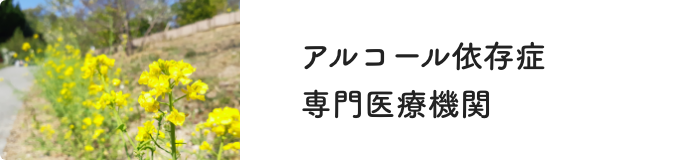お知らせ
news

- コラム
- 父と娘、たまに医師。 第5回
父と娘、たまに医師。 第5回

平和会地域緩和ケアサポートきずな
加納 麻子 (日本緩和医療学会 専門医)
緩和ケア医が、自身の父の最終章に関わってきた思いを綴るエッセー。6回にわたって掲載します。
「ごろごろ出来ないじゃないか!」
父の病は進み、和室の布団からトイレへの往来すら命がけの仕事になりました。頻繁に転び生傷が絶えず、途中でぐったり力尽き倒れることもありました。せめて立ち上がり易いようにとベッドを提案するも、父は頑なに受け入れません。
ある夜、父がリビングで過ごしている間に、こっそり母と一緒に父の部屋にベッドを組み立てました。意外に便利だと思ってくれるのではないかと期待を込めて。しかし、部屋に戻ってきた父は「ごろごろ出来ないじゃないか!」と激怒しました。寝返りや這うことで移動するには布団の方が都合よかったのでしょう。良かれと思ってやった母と言い合いになるものの、父は折れませんでした。なぜそこまで怒ったのか。父は自分のことは自分で決めてきた人です。それが尊重されなかったことにこそ、父は本気で怒ったのかもしれません。母と私は組み立てたばかりのベッドを解体し、父は布団生活を続けました。
這うことすら出来なくなっても父はおむつを使いたがりませんでした。これまで通りの暮しを続けることが、父にとって決して譲れない大切な事のようでした。母は父を座布団に乗せてトイレまで引っ張るという根気強い介護をしていました。母から状況を聴いて、いつ亡くなってもおかしくないと思い始めたその夜、父は突然にして昏睡に陥りました。回復する事態ではないことは明らかでした。私は「病院に搬送せず、ここで看よう」と母に言い、遠方に住む姉に電話しました。
父を囲み母と姉と共に雑魚寝。私は父の脈を触れながら隣で眠りました。ベッドでなく布団のままにしてよかったと改めて思った夜でした。
まるで熟睡しているだけかのような静かな時間が過ぎ、翌日の八月四日の夜、父は文字通り畳の上で亡くなりました。
父の死亡確認を娘の私がする。胸に聴診器を当てる。そうなることはわかっていたはずでしたが、不思議と心づもりが出来ていませんでした。私はその時の感情を表す言葉を、今もみつけられていません。

麻のように真っすぐ育ってほしいとの願いから「麻子」と名付けてくれました
サイト内ページ一覧