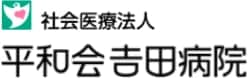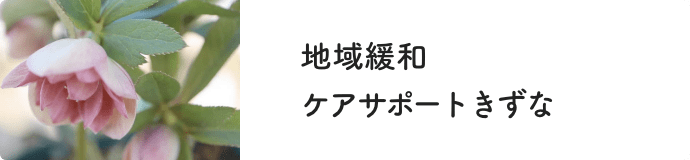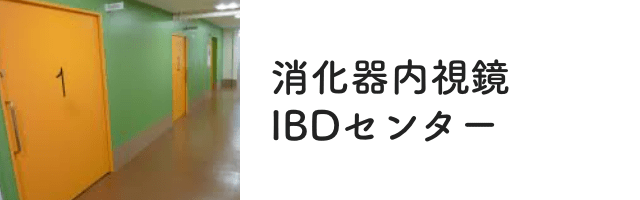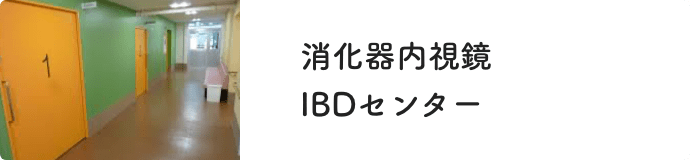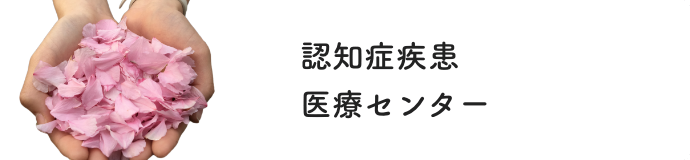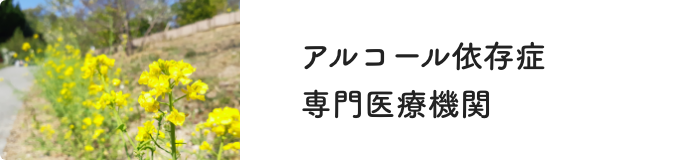お知らせ
news

- コラム
- 父と娘、たまに医師。 第6回
父と娘、たまに医師。 第6回

平和会地域緩和ケアサポートきずな
加納 麻子 (日本緩和医療学会 専門医)
緩和ケア医が、自身の父の最終章に関わってきた思いを綴るエッセー。6回にわたって掲載します。
「おれの写真を撮っておいてくれ」
「結婚式の時、おれの写真を撮っておいてくれ」今から4年前、私の結婚式が近づいてきた頃、父はそう言いました。理由は尋ねなくても分かりました。久しぶりにネクタイを締める機会に、自分の遺影となるポートレート写真を準備しておきたかったのです。母は「縁起の良い日に、縁起でもないことを」とつぶやきました。私は「カメラマンに依頼しておくね」と約束しました。
まだその頃は症状もなく元気でしたが、がんだけではなく他にも疾患を抱えていました。後期高齢者となり同世代の友人達に先立たれる中で、父は静かに終い支度を進めていたようです。娘の結婚式と披露宴の合間に自分の写真を撮影。カメラのレンズを見つめる父の心境はどのようなものだったのでしょう。肩の荷が降りたような気持ちであったでしょうか。自分のこれからに思いを馳せていたのでしょうか。
それから2年後、その写真を使う時が来ました。自分の部屋の畳の上で息を引き取った父の体を、家族みんなできれいに拭き、母が仕立てた浴衣を着せました。そして、父の部屋で身内だけの堅苦しくない葬儀をして玄関から送りました。悲しくも幸せな別れの時でした。
遺品を見ると、重要な書類は全て分かりやすくまとめられ、いつその時が来ても残された私たちが手続きに困らないようにしていました。どこまでも自分より周りを気遣う父でした。
母は欠かさず遺影の前に食事を供えてきました。ひとり暮らしのようでいて、なお父と暮らしているかのように。母が「お父さんが台所に入ってくるのが見えてん。おどけた顔して。わかるやろ、あの顔」と言ったことがありました。私はそれを不思議とも思わず、自然にかつての姿が思い出され、(ああ、お父さんはやっぱりいるんや)と涙が溢れました。
父が亡くなった翌年に、私はもうひとつ大きな喪失を経験しました。悲しみでとうてい乗り切れそうにない苦しさのなか、父が必ず守ってくれるはずだという確信が、救いとなりました。見えなくとも確かに存在する父がいます。生きていた時よりもずっと近くにいて、時に助けてくれさえするのです。
***
これまで全6回に渡り、連載をお読みいただきありがとうございました。
ご自身の大切な人との別れを思い出し、悲しみを感じた方もおられることと思います。「悲しみは亡くなった人が訪れる合図だ」ときいたことがあります。深い悲しみの中にいる方が、またゆっくりと歩き出せますよう心から願っています。

2018年、父と歩いた美しい秋の日でした
サイト内ページ一覧